・静電容量は2種類あるよ
よく耳にする言葉ですが、意味をちゃんと理解していますか?

簡単に言うと
静電容量とは
導体の電位を1[v]上げるのに必要な電荷量、またはコンデンサなどに蓄えられる電荷量
です。
静電容量の元々の意味は前者なのですが、コンデンサなどで後者の意味として使われるようになったのだと思います。
ただ、自分としては前者の意味を覚えておく方がいいと思ってます。
どちらも最後に電荷量とあるように、静電容量は電荷量を表していると考えるといいかもしれません
具体的なイメージを見ていきましょう!

詳しく言うと
最初に言っておきますが、静電容量には2種類あります!
まず、1つ目が「導体が1つだけの場合」です

図のように、導体球に電荷$Q$が与えられ、導体球の電位が$V$のとき、この導体球の静電容量Cは$C = \frac{Q}{V}$と表されます。
この場合の静電容量とは、「導体の電位を1[v]上げるのに必要な電荷量」となります。
次に、2つ目が「導体が2つ以上の場合」です。ここでは導体が2つの場合を考えます。

図のように、導体球にそれぞれ$Q$と$-Q$が与えられ、導体球間の電位差が$V$のときも、静電容量$C$は$C = \frac{Q}{V}$と表されます。
この場合の静電容量とは、「導体の電位差を1[v]上げるのに必要な電荷量」となります。
もしこれがコンデンサーならば、「蓄えられる電荷量」と考える方がいいでしょうね
つまずきポイント

静電容量の公式には、$C = \frac{Q}{V}$と$C = \frac{\varepsilon_{0}S}{d}$の2つがありるけど、2つの違いは何なの?

こう思ったことがある人も多いのではないでしょうか?
単純に「公式が2つある」という情報だけ覚えてしまっては、実際に問題を解くときに混乱してしまいます。
$C=\frac{ε_{0}S}{d}$という公式は、元々$C=\frac{Q}{V}$から導出した公式で、コンデンサのときにだけ使える公式です。(導出は調べてください)
もっと言うと、導体の面積が十分に広く、極版間の距離が非常に小さいときに使えます。
だから、この条件を満たしていない場合は、$C=\frac{ε_{0}S}{d}$を使えず、$C=\frac{Q}{V}$を使うしかありません。









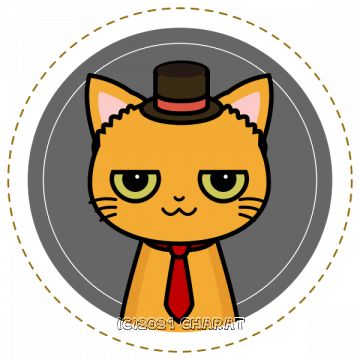

初学者におすすめな参考書を調査してまとめてみました。良かったら参考にしてください。